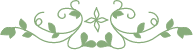※ゲーム上、話しすぎると不利になる可能性があります。
ホレシュ氏を殺害する直前まで、盗みにはいったのが彼の家だったことを俺は知らなかった。
家族そろってこの町場に移住してきたのは俺が幼い昔。両親はすでに他界した。
朝から晩まで身を粉にしても、商店の下働きで得られる給金は悲しいほどに少ない。
温室育ちでわがまま放題だと噂の領主の子女たちが恨めしく思える。
俺には金が必要だった。病に侵されていく妹の命を長らえさせるために。
慌ただしいぶどう酒の送達の道中、町場の外れにひっそりとたたずむ屋敷に目をつけたのは、つい最近のこと。
盗みにはいる覚悟が決まり、久々に仕事の休みを都合できたのが昨日だった。
昼が過ぎた頃。俺は屋敷に到着した。門前に広がる庭の手入れはいきとどいていない。家主が留守にしがちである証拠だ。
屋敷正面の玄関を閉ざす鉄の扉はいかにも重厚である。俺はかねてからの計画どおり、屋敷の裏に回り込み、家に接するように生えている木をよじのぼる。
そして、2階の窓のはめ殺しのガラスを蹴破って中に忍び込んだ。これは正面の玄関を除いて、唯一の侵入経路であった。
その書斎には、インクの匂いが立ちこめていた。地図の記された羊皮紙の束がそこかしこにひしめいている。机の上には、水さえ汲まれていない陶器の花瓶。忙しさのあらわれだろうか。
俺は部屋じゅうをひっくりかえして金品を物色する。
かき集めることのできた金貨はまずまずの量だった。その折りに、図らずも家主にまつわる手がかりをいくつか得ることにもなった。
「・・・ホレシュ殿。優れた地図帳の数々、たいへんに重畳であり・・・」
貴族からの感謝と慰労の旨を伝える書簡。この文面で、俺はようやくこの屋敷の主が高名なホレシュ氏であることに気づく。
「・・・お父様。体調は優れませんが、ポロウ盆地で一緒に暮らせることを希望にしています。こちらの空気はとてもきれい。いつか必ずこの病も治るでしょう・・・・」
半年以上前の日付の便箋。ホレシュ氏には愛娘がいたようだ。衣装棚からは若い女が着るような毛織のチュニックも見つかった。使用の痕跡はなく、まっさらなままだ。
書斎の扉が開いたのは、ほんの数秒の感慨にふけっていたときだ。
「悪いことは言いません!いっしょに審問官のところへ出頭しましょう」
いたのは、整った面立ちをこわばらせる中年の紳士。両掌を向け、こちらを窘めている。
窓の割れる音を聞き、足音を殺して階段を上ってきたのだろう。
俺は無意識のうちに机上の花瓶を手にとっていたようだ。
気づけば、頭部への一撃によって絶命したホレシュ氏が書斎中央に横たわっていた。
逃げるように階段を下りた1階の広間で、俺の心臓は早鐘のように高鳴っていた。
何分も呆然としていたように思える。気を取りなおさせたのは、屋敷の正面の玄関からあらわれた来訪者だった。
「あら、先客がいらっしゃったのね。私はシリーンと申します・・・」
「ファリドです。自分も今しがた到着したばかりで・・・お留守でしょうか」
そんな経緯で、俺はホレシュ氏との出会いについて、でまかせで塗り固めたわけである。
シリーンが気まずそうに屋敷を辞したあと、俺もそこを離れることにした。
彼女がなぜこの屋敷に入って来られたのか、正面の玄関から出ていくときにわかった。
鉄扉の錠はひどく錆びついており、鍵はもはや役割を果たしていないのだった。
町場のあばら家では、病の妹が床にふせって俺の帰りを迎えた。
「・・・今日は仕事、早かったのね。ごめん、私がこんなだから・・・」
「病気なんて、俺が稼いでくればすぐに治せるさ」
どんな罪を背負おうとも。取り返しがつかなくなったとしても。
「そうだ、とある金持ちから気に入られてさ、金貨をいくらか恵んでもらったよ。
まさしく幸運だ。・・・これからのことはあんまり心配するな」
まさしく。・・・嘘をつくときに口ずさむ俺の癖だ。
まさしく。まさしく。・・・それが本当であると、自分自身へ言いきかせるように。
そして今。この尋問室に喚び出され、俺は取り調べを受けている。
おそらく、ホレシュ氏の知り合いでないことが発覚すれば、俺は疑いの目から逃れることはできないはずだ。もっともらしい話を用意しなければならない。
これからの尋問では、他の3人の話をよく聞いておく必要があるだろう。
ホレシュ氏の死後にのこされる彼の家族のことを想像するたび押し寄せる罪悪感。しかし俺はそれを振り払う。
絶対にこの窮地を脱する。そう、妹のためだ。
後悔する暇はない。まさしく、あれはやむを得ない殺人だったのだから。